
Profile
-
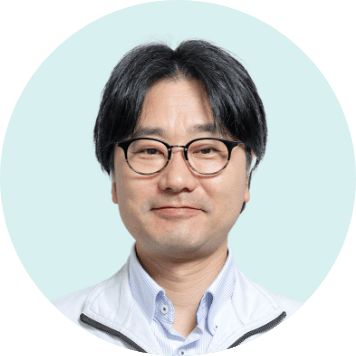
-
T.H
1998年入社
技術開発部

-

-
Y.I
2006年入社
技術開発部
Cross TalkYKIスタッフ対談
技術を生み出し、技術を育てる
技術開発への熱い思いが
業界の発展を担っていく
技術を生み出し、
技術を育てる
技術開発への熱い思いが
業界の発展を担っていく
-
01 “こんなものがあればいいな”を現実に
この世にないものを作り出していく
-
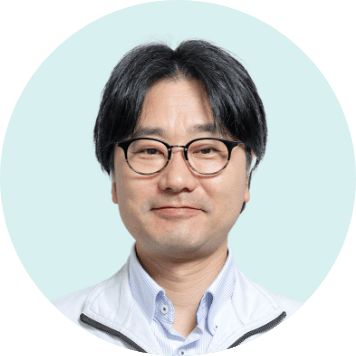
T.H - 僕たちの部署では、部品を作るための加工や検査の技術の開発を行っています。AとBという技術を組み合わせて新しいCという加工技術を生み出すとか、Aという技術をもっと早くするためにCを追加させるという感じです。
-

Y.I - 今はまだ量産できていないけど量産化を実現したいものはたくさんあり、より軽く、より早く、より低コストにしたいという目標も常にあります。そのための構想検討、試験と評価を繰り返し、この世にないものを作り出していく部署です。
-
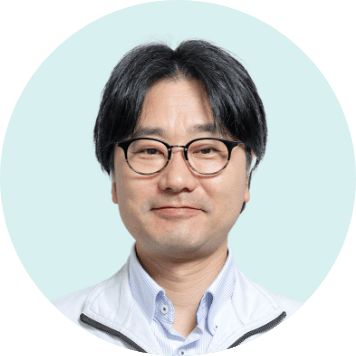
T.H - 例えば、2年後に車種開発がスタートするという計画を聞けば、そこをターゲットにそれまでに挙がっていた「こんなものがあればいいな」の実現に向けて動き始めます。開発のタイミングに入れられるよう新技術のアイデアをカタチにすることが仕事です。
-
-
02 どうすればいいものができるか
時間をかけてじっくりと見定めていく
-
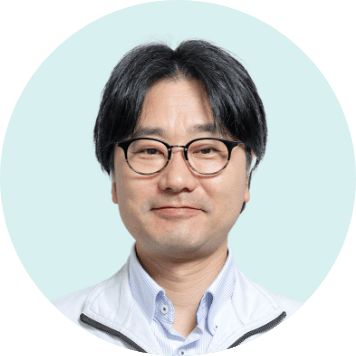
T.H - 開発テーマの決定には市場調査が欠かせません。業界の動向はもちろん、加工メーカーや展示会で得るヒントもアイデアの源になります。様々な視点でニーズを探り、自分たちが持つ技術をどう組み合わせればいいものが作れるか、時間をかけて探っています。
-

Y.I - とはいえ新しいことを考えるのは難しいですし、上手くいかないことの方が多いですが、そこは皆でアイデアを出し合って工夫を重ねます。それぞれの得意分野を活かしながら新たな解決案が生まれるような時間は楽しいですね。
-
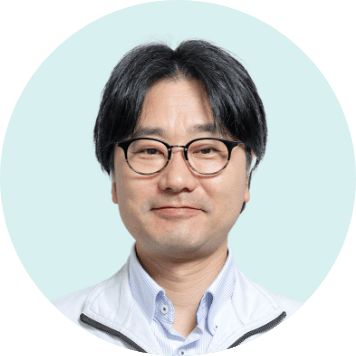
T.H - この部署にいるといろんなことが見えてくるんです。設計、プレス、接合、や塗装設計から品質保証まで考えることは多岐に渡りますから。だからこそ、課題解決を繰り返した先には経験という引き出しと視野が増え、それがこの部署の面白さだと思っています。
-
-
03 モノづくりを支えてきた自動化の歴史
目指すは人のような柔軟性の高い技術
-

Y.I - 僕は技術開発部に来た頃から、画像処理等での自動検査技術の開発を目指してやってきました。まだまだ、人でないと十分に判断できない検査が多いですが、モノに出来た技術は積極的に量産適用出来るよう関連部門と一緒になって検討・導入に努めていました。
-
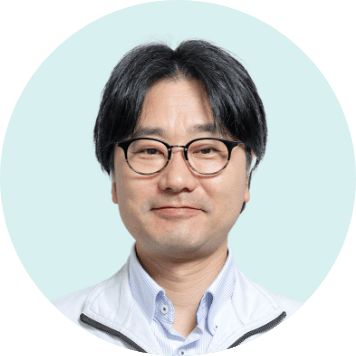
T.H - 自動化できていないところでいうと、検査のほかに、ロボットの移動を伴う組付け作業があります。あとは細かい部品の向きを微調整して置く、組み合わせてはめるといった、人が両手を器用に使ってやっている作業はロボットでやると手数や装置が多くなり過ぎて、まだまだ自動化が進んでいません。
-

Y.I - 人の手って素晴らしい性能を持っていて、工学的にあり得ない軽さと力強さと柔軟さを持ってるんです。人間が無意識にやっている動作をロボットで実現するとなると、すごい手数になってしまい、自動車のように部品の多い製品では逆に生産性が上がらなくなる場合もあるんです。
-
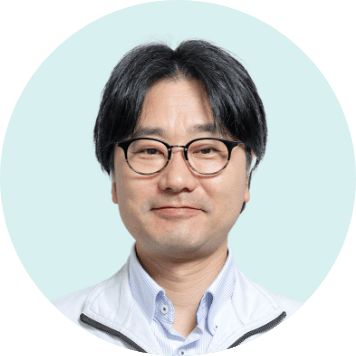
T.H - 人間ならではの“モノを取って置く”という作業が従業員の60%を占めているんですよ。そのあたりの技術やからくりをどう開発していくかは自動化の未来に影響しますし、どこをロボットが担うべきなのかも考えないといけないですよね。
-
-
04 できていないことを変えていく
その先にある、自動車産業の未来を見据えたい
-
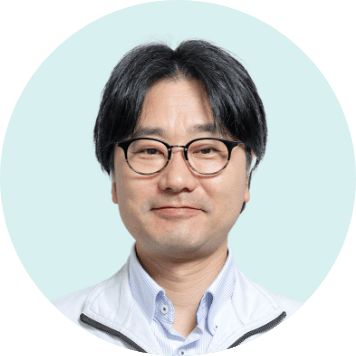
Y.I - 先ほどの生産性の話でいうと、人の手のほうが早い場合があるのは、一度に多種類の部品を組付ける自動車業界ならではかもしれません。工程や部品の数だけロボットを置くスペースも必要となると、どうしても人が残る業界であるともいえます。
-

T.H - そうですね。自動化すればいいというだけではなく、僕たちが考えるのは新しい設備に変えても収益が出るかという側面もあります。ただ、どうしても重たい部品を対象にするときは人だと辛い作業になるので自動化を目指すとか、優先順位を考えながら人とロボットのバランスをとることが大切です。
-
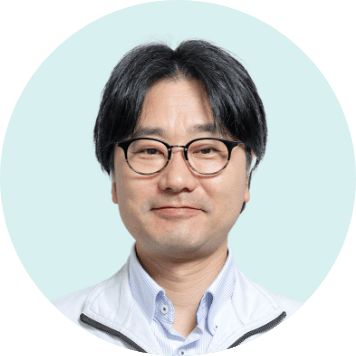
Y.I - ただ、ここ最近ではAIやヒューマノイドといった、人の柔軟性、判断力を持つロボットの開発も急速に進んでいるので、今まで自動化が難しかった事が突如として当たり前に出来る未来もあるのかもしれないですね。自分達の常識に捕らわれず、これらの技術も積極的に取り込んで、ワクワクする工場にしたいですね。
-

T.H - あとは引き続き軽量化の向上ですね。材料が進化するにつれて、それを加工する技術も高度になります。自動車の電動化は進んだけど、重たいバッテリーを改善しなければ車両全体の重量も下がりません。カーボンニュートラルの観点から見ても、様々な視点でこれからも軽量化への道を探求することが使命だと感じています。
-







